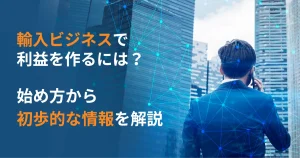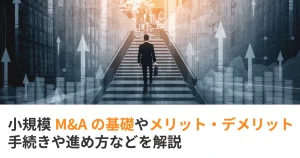業務提携とは?基礎から違いやメリット・デメリットをわかりやすく解説
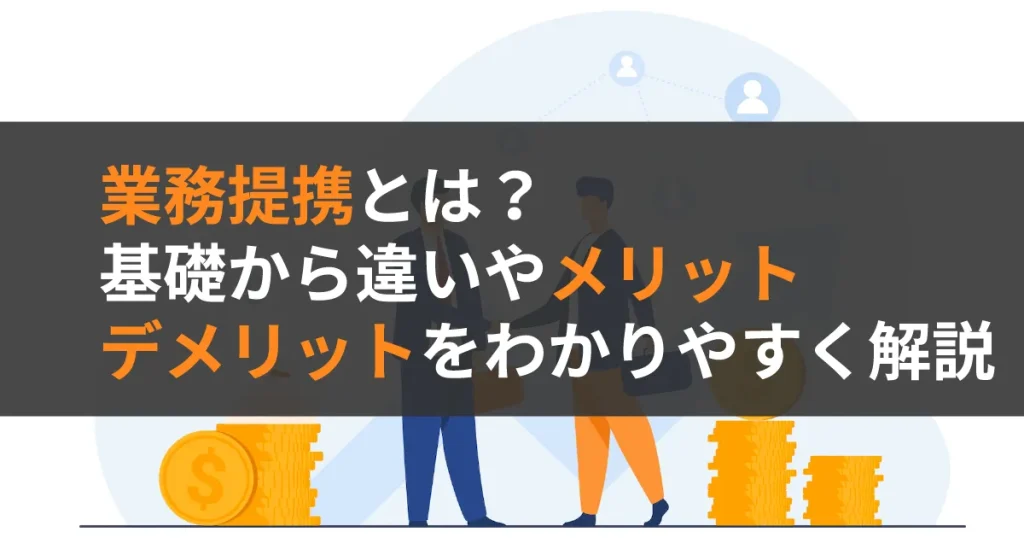
近年はDX推進の波が中小企業にまで波及しており企業間における資本提携や業務提携のニュースを目にする機会も増えました。
業務提携や資本提携、業務委託など類推するワードがビジネス上には多く見られます。
この記事では業務提携に関する基礎的な知識から資本提携などとの違いやメリット・デメリットを解説します。
業務提携とは
他社の経営リソースを活用して事業成長を行う手法に業務提携があります。
似た用語に事業提携がありますが、
事業提携
特定の分野の事業全般を複数の企業が提携して遂行する
業務提携
特定分野における特定の事業内容を複数の企業で遂行する
という違いがあります。
どちらも事業成長を目的とした手法ですが、業種や企業間の契約内容によって提携内容は異なります。
また業務提携と同じく事業成長を図るために締結される企業間契約に資本提携とM&Aがあります。
業務提携と資本提携の違いについては後述します。
業務提携の種類
業務提携の主な種類には「販売提携」、「技術提携」、「生産提携」があります。
販売提携
パートナー企業同士で商品やサービスに関わるリソース(流通、人材、技術、ノウハウ等)を提供し合う提携が販売提携です。
効率よくスピーディーに販路の開拓や新規事業への参入ができるようになります。
販売提携における契約形式には下記があります。
販売店契約
パートナー企業の製品を購入して、自社の店舗にて購入した商品の販売を行います。
自社の管理のもとに運用され価格設定も可能です。自由に管理ができる反面、在庫を持つリスクと消費者と直接的に関わるのでクレーム受ける等の責任も発生します。
代理店契約
販売店契約に近似した内容で、パートナー企業の商品を購入するまでは販売店契約と同様ですが、購入した商品の販売計画や管理は販売側の管理下にある形式です。
価格設定や購入者対応も販売側が対応します。
フランチャイズ契約
フランチャイザ―とフランチャイジーの間で締結されるフランチャイズ契約も、業務提携における販売提携の一種です。
本部企業が保有する使用権、販売権、ノウハウを加盟店であるフランチャイザ―が対価を支払って販売活動を行います。
技術提携
パートナー企業同士で既にある技術を提供しあう事で新しい技術や製品開発を行う共同開発、もしくは一社の技術を有償で提供して新商品の開発や生産を行う提携手法です。
複数企業で技術を開発したりノウハウを共有しあうのでスピーディーで効率の良い技術開発が可能になります。
生産提携
パートナー企業に対して生産や生産工程の一部を委託する提携方式です。
委託する側には生産コストを抑えて生産量を増加できるメリットがあり、委託される側には工場や設備の稼働率向上のメリットがあります。
人気のある商品で自社での生産が追い付かない場合に適用されます。
OEMやODMといった方式も生産提携にあたります。
業務提携の流れ
業務提携をおこなうにあたってのフローは主に下記の項目となります。
提携先を選定
先ずは業務提携を行う目的を明確にする必要があります。
自社の持つ強みと不足している領域を分析し、不足しているリソースを補いシナジーが創出される提携先企業を選定します。
この時点で目的を完遂するにあたっての戦略は具体的にしておくべきです。
提携業務の内容を決定
業務提携は複数の企業間による手法ですが、片方の企業のみにメリットがあるだけでは成立しません。
参画している全ての企業がwinwinでなければいけません。
一緒に目的を達成できそうな提携企業が見つかったら交渉に入ります。
自社の強みだけでなく相手企業の得られるメリットも明確にして伝えましょう。
役割を決定
パートナーに相応しい企業を選定し合意を得られれば秘密保持契約の締結に進みましょう。
締結後は本格的な交渉に入り、それぞれの企業における役割を決定します。
スムーズに役割分担を決定するためには、予め業務項目の洗い出しをしておきましょう。
担当する分野の決定と同時に、後でトラブルにならないように責任の所在も明確にしておく必要があります。
企業間での目的をしっかりと共有し、綿密にコミュニケーションをとっていないままに業務提携が進んでしまうと契約後に意識のズレが生まれてしまいます。
最悪の場合には訴訟まで発展する事も視野に入れた上でのリスクヘッジも求められます。
役割分担が決まり交渉がまとまった所で基本合意書を取り交わします。
最終的な契約の締結前にフィジビリティスタディ(業務提携が事業として成立するかの事前調査)やデューデリジェンス(財務・法務に関する事前調査)を行うことが通例となっています。
業務提携契約書を作成する
交渉時に決めた内容を契約書に盛り込み、最終的な契約書である業務提携契約書を作成します。
専門的な知識が必要になることと、内容に不備がないかを確認するために弁護士や社外の専門家にアドバイスを受けた上で契約を締結しましょう。
契約締結後は、契約内容に基づき業務提携を遂行していきます。
業務提携・資本提携の違い
業務提携と似た用語に資本提携があります。
資本提携とは
企業間において資本の移動(自社で保有している株式や新株を通しての増資)が行われる提携手法を指します。
資本提携における資本の移動では会社の経営権までの移動は発生せず、お互いに独立した常態で財務支援や業務提携が行われます。
業務提携と資本提携では資本の移動が発生しないという点において大きく違いがあります。
しかし、他企業の経営リソースを活用して事業成長を行うという点においては共通点があり、業務提携は資本提携や同じく共通点のあるM&Aとの比較検討はよくされます。
業務提携と業務委託の違い
委託した業務が遂行されて対価を支払う流れとなり、締結する契約は業務委託契約です。
業務委託とは
ある特定分野の業務を外部に委託することを指します。
一方、業務提携とは複数の企業が相互に経営リソースを補完し合い、特定の業務において協力し合う形態を指します。
また業務委託では、受託した側が業務に対する責任が大きくなる側面があります。
ただ販売提携や生産提携の契約内に委託の条項が入っているので、業務提携と業務委託は近しい手法であるとはいえます。
業務提携のメリット
業務提携においては自社に不足している経営リソースを他社のリソースで補える特徴があります。
資本提携やM&Aとは違ってコストや手続きも抑えられるので複数のメリットを持ちます。
リスクの回避
資本提携やM&Aと比較した時に、他社と協力関係を築き相互に経営リソースを補完しながら事業成長を目指す点は共通しています。
しかし、業務提携には資本提携やM&Aとは違って資本の移動がありません。
資本の移動が発生しなければ経営権の移動もなくお互いに独立性を保っていられるのでパートナー企業の業績悪化による影響も受けません。
そのため業務提携はリスクは最小限に抑えて事業成長を狙える手法といえます。
契約関連の簡易さ
複数の企業間による協力関係の強化でシナジー効果を得られるのは資本提携やM&Aも同じです。
業務提携がそれらの経営手法と異なる点は、企画・検討から契約締結までのスピードが短く契約手順も簡易であることが挙げられます。
前述した通り業務提携には資本の移動はなく、パートナー企業の業績から受ける影響も少ないのでデューデリジェンスも比較的簡易に済みます。
資金があまり必要ではない
業務提携では複数の企業が経営リソースを持ち合って補完し合うので多額の資金を必要としません。
これがM&Aや資本提携であれば株式の取得などに多額の資金を必要とします。
パートナー企業の経営リソースを上手く活用することで低資金での提携が可能です。
業務提携のデメリット
業務提携にはメリットだけではなくデメリットも持ち合わせています。
業務提携を検討している場合にはデメリットに関しても十分に考慮しましょう。
情報の漏洩
業務提携の特徴である経営リソースの補完は、裏を返せば自社の情報や技術、ノウハウをパートナー企業と共有してしまうことでもあります。
自社の情報が相手側に漏洩するだけでなく、パートナー企業の情報を意図とは関係なく流出させてしまうリスクも発生します。
契約内容によっては情報漏洩から訴訟にも発展する事も想定されます。
漏洩のリスクを考慮するのであれば、秘密保持契約の締結や情報管理体制の構築をしっかりと行い、提携プロジェクトに参画している従業員の行動管理も求められます。
成果をめぐるトラブル
技術提携や共同開発において新しい技術や製品の開発を行った場合、費用の負担額や特許をめぐってのトラブルが起きやすい留意点があります。
また開発した製品が売れた時の利益配分も同様です。
これらの成果をめぐるトラブルを回避するためには、利益の配分や負担額に関しても契約内容に盛り込み業務提携後に揉めないためのリスクヘッジが必要です。
関連する記事について
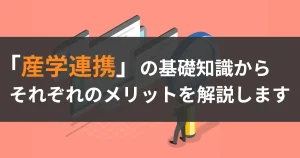
業務提携の注意点
様々なメリットを持つ業務提携ですが、企業間同士でトラブルになりやすいデメリットもあります。
トラブルを事前に回避するように下記の留意点に気を付けましょう。
契約書でトラブル防止
業務提携は企業同士で経営リソースを出し合って事業成長を図ります。
しかし共同で技術を提供し合って生まれた新技術や製品をめぐってトラブルにもなりやすい側面があります。
そのようなトラブルを事前に回避するためにも、契約書内には成果物の帰属先や利益配分、負担する費用、業務内容の分担などは明記しておくと良いでしょう。
秘密保持契約を結ぶ
情報漏洩やノウハウや技術の流出リスクを回避するためにも、秘密保持契約の締結を行いましょう。
異なる企業同士で経営リソースを出し合う業務提携では、秘密情報を共有してしまうこともあります。
自社の情報が外部に漏れることも阻止したいですが、
パートナー企業の機密事項を入手して意図せず流出させてしまい損害賠償を求められる等のリスクもあります。
秘密保持契約には漏洩してはいけない事項の明記を行い、万が一に情報漏洩や流出が起きた場合を考慮して損害賠償に関する記載もあると良いでしょう。
契約書の作成に関しては専門的知識が必要です。
作成に関してはプロである弁護士に依頼しましょう。
まとめ
業務提携は、資本提携やM&Aとは異なり資本の移動がなくコストの面でも実施がしやすい経営手法です。
複数企業と協力関係を築いて事業成長を目的としていますが、自社の独立性は保たれ効率が良く、スピーディーな事業拡大に大きく寄与します。
しかし、一方では情報漏洩や契約に関するトラブルのリスクも潜んでいます。
企業間での齟齬がでないように密なコミュニケーションや交渉を行い、綿密な契約書の作成、入念な準備をして業務提携を上手に活用しましょう。