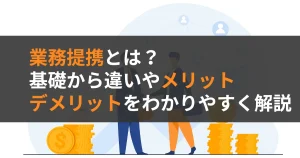小規模M&Aの基礎やメリット・デメリット、手続きや進め方などを解説
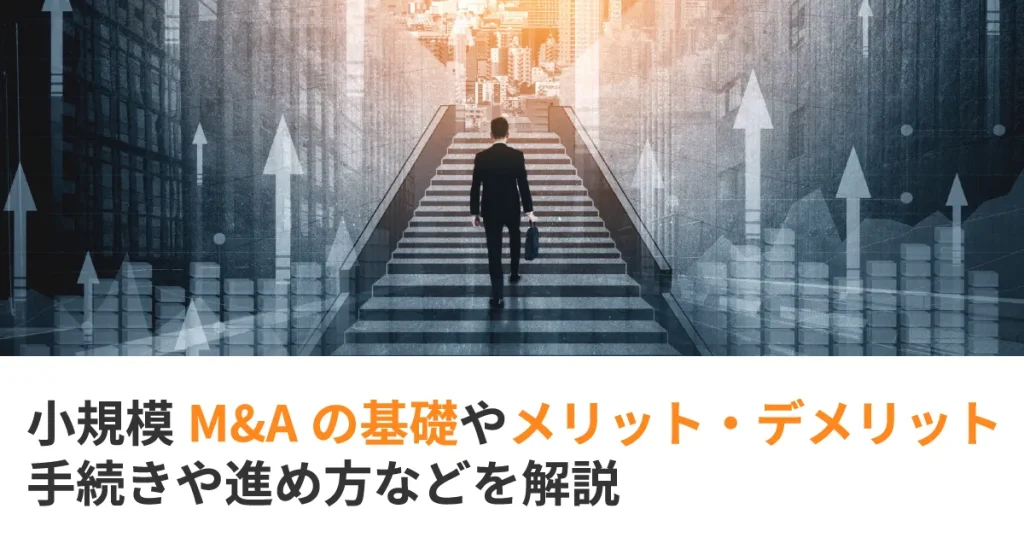
現在の日本では事業承継や後継者不足が中小企業において社会問題化しています。
それらを背景とした小規模のM&Aが近年は増加中です。
こちらでは小規模M&Aの基礎的な知識からメリット・デメリット、小規模M&Aの手続きや進め方を解説します。
小規模M&Aとは?
小規模M&A、スモールM&Aと呼ばれる譲渡金額が少額のM&Aが増加しています。
実際小規模M&Aとはどんな形態なのか、また小規模M&Aが増えている背景を説明します。
小規模M&Aの定義
小規模M&Aは法律で定められた条件がある訳でもなく、業界や事業者によっても定義はバラバラです。
その為細かい定義はありませんが、売り手・買い手双方(片方の場合もあり)の年商が1億円以下、M&Aでの売却額が1億円以下のラインが、どの業種でも小規模M&Aとして認識されています。
小規模案件M&Aが増えている理由
小規模のM&Aが増加している背景には下記があります。
経営者の高齢化と後継者不在
中小企業における後継者の不足は大きな社会問題です。
また中小企業では2025年までに245万社の経営者が70歳を超えるともされており高齢化も大きな課題となっています。
企業経営者の年代で後継者の不在率を見ると、60代で39.2%、70代で28.2%、80代で22.6%となっており高齢企業での後継者不在が浮き彫りになります。
事業承継、経営資源の引継ぎ
中小企業では約6割以上が事業承継の課題を抱えているという統計データもあり、後継者不在の10万2,226社の内5万1,721社(構成比50.5%)では「後継者の不在、未定」となっています。
事業承継の方針が明確にならない、計画が立たられない企業が多い実態が現在の日本にはあります。
M&Aは事業承継や経営資源を第三者へ引き継ぐことを目的としており、高齢企業にとっての事業承継の代替手段として非常に有効なのです。
新規事業への参入、経営の多角化を目指す起業
小規模M&Aは売却側だけではなく買い手側にもメリットが多くある経営手法です。
自社の経営成長を考えた時に新規事業への参入や事業の多角化が必要になるタイミングがあります。
小規模M&Aでは自社には揃っていない経営リソースを短期で調達することができるので、新しい市場を意識している企業にとっては効率の良いビジネス手法です。
新型コロナウイルスの影響
2019年後半から本格的に蔓延した新型コロナウイルスの影響で2020年のM&A件数は前年を下回りました。
しかし2021年に入ると1月~6月の上半期のM&A件数は2020を上回り、過去最高件数だった2019年1月~6月の件数も超えました。
実は2021年以降は企業におけるM&Aが活況となっています。
小規模M&Aのメリット・デメリット
小規模M&Aにはそれぞれメリット・デメリットが存在します。
売り手側、買い手側毎に小規模M&Aのメリット・デメリットを見てみましょう。
売り手のメリット
小規模M&Aには会社や事業を承継できる以外にも以下のメリットがあります。
赤字でも売却が可能
小規模M&Aにおいては黒字の企業や事業しか売却できないかといえばそんなことはありません。
債務超過や赤字がある企業でも、人材や流通チャネル、取引先、技術やノウハウといった経営リソースを目的に買い取られるケースもたくさんあります。
特に買取側に経営手腕があれば売却後に経営の立て直しがされる場合もあり、借入時の個人保証も肩代わりしてもらえるメリットがあります。
廃業コストがかからない
小規模な企業であっても廃業時には数百万円の費用が必要です。
廃業ではなく小規模M&Aでの売却ができれば廃業コストは発生しません。
売却益、創業者利益の獲得
前述の通り廃業コストがかからないメリットが小規模M&Aにはあります。
更にM&Aが成功して会社や事業の売却が実現すれば売却益を得られます。
財務状況も優良であれば創業者利益を得ることもあり、それを基に別の事業を立ち上げるなど再チャレンジをする経営者も珍しくありません。
通常のM&Aよりも短期でおこなえる
通常のM&Aよりも小規模での実施となるため、売却にかかる期間も短く済みます。
売り手のデメリット
売り手のデメリットとして下記には留意する必要があります。
想定していた売却額にならないこともある
小規模M&Aの買い手に大企業や有名企業がつくことはよくあります。
小規模M&Aの売り手は中小企業であり、M&A自体が初めてのケースが目立ちます。
交渉ごとに関しては実績豊富な大企業側の方が長けており、想定していた金額で売却できない懸念点もあります。
全ての売却条件が通ることは難しい
上記の売却金額以外にも従業員の待遇や個人保証の肩代わりなど、M&Aには様々な条件があります。
小規模M&Aといえども買い手側が全ての条件を飲むということは稀です。買い手にも様々な事情があるので、どの程度の条件まで飲んでもらうかの落し所を決めておく必要があります。
売却後の主導権は買い手企業にあり
小規模M&Aであっても売却後の経営権は買い手側に移転します。運営自体は買い手側のコントロール下にあり経営方針には従わなければいけません。
買い手のメリット
一方、買い手の得られるメリットは下記になります。
投資金額が回収しやすい
小規模M&Aによるバリュエーション(売買額の算定)には年倍法(年買法)が用いられることが一般的です。
年倍法による算定方法は、時価純資産 + 修正営業利益 × 3年~5年分で算定されます。
小規模M&Aの場合は売買金額が少額であるため、買取企業のスケールメリットを活かすことで投資回収のスピードは上がりやすいといえます。
コストパフォーマンスの良い独立・起業が可能
0から企業することを考えると事業計画書の作成や従業員の雇用、設備投資など準備にはそれ相応の時間とコストがかかります。
小規模M&Aであれば経営リソースや環境が整った状態で獲得がしやすく手間を省いて効率的に独立や企業ができます。
また小規模M&Aには個人や小規模事業者でも手の届く金額のM&A案件もあるので、企業や独立を検討しているのであればリサーチをして売り手側にアプローチを掛けてみるのもオススメです。
リスクの分散
大企業だけでなく中小企業も事業拡大戦略にM&Aを活用しています。
小規模M&Aでは取引金額1億円以下の案件がポピュラーで1,000万円を下回るケースもよくあります。
中小企業であってもM&Aによって複数の企業を獲得し、事業の多角化を図ることが可能です。赤字の事業が発生しても別の事業で黒字化できればリスクの分散にもなります。
買い手のデメリット
買い手のデメリットとして留意すべきポイントは下記になります。
簿外債務などの発覚
売り手が小規模の零細企業であったり個人事業主である場合、会計処理が外部の会計士であったり管理が行き届いていないことがあります。
売却側が自社の経理状況をよく把握できてないケースもあるので、M&A後に帳簿に記載されていない簿外債務が発覚することもあります。
帳簿に乗っていないので交渉時にはスルーされてしまうリスクが高いので、買取側においてはデューデリジェンスを徹底する必要があります。
人材や取引先を継続できない
小規模M&Aにおいては、旧経営者との関係性で従業員や取引先が繋がっていることが多くあります。
そのためM&A後に新しい経営者や社風と合わずに従業員が退職してしまったり、顧客や取引先が離れてしまうケースも目立ちます。M&A後にも旧経営者には会社に残ってもらえる等のリスク回避策が必要です。
競合が多い
現在の小規模M&A市場は活況です。少額、小規模で実施がしやすくメリットも豊富であれば小規模M&Aで別の企業や経営リソースを獲得したい企業は後を絶ちません。
いわゆる競合相手が多い状態であるので欲しい案件であっても確実にM&Aができる保証はありません。確実に手に入れたい案件があるのであれば常日頃からアンテナを高く保ち、入念な情報チェックが欠かせません。
小規模M&Aの事例
実際に小規模M&Aで成功した事例をご紹介します。
後継者や設備投資などの問題に関する事例
茨城県水戸市にある「ときわコンピュータサービス株式会社」では、大手電機メーカーを退職して起業したオーナーが80歳を迎えるにあたり小規模M&Aによって東京のIT企業へ会社を売却しました。
創業36年のシステム開発会社であったときわコンピュータサービス株式会社ですが、オーナーの加齢による身体の負担と後継者不在を理由に75歳から約5年に渡って後継してくれる企業を探していたそうです。
旧オーナーと同等のスキルを持ち、従業員や取引先に対しても同等のサービスとマネジメントをしてくれる買取側企業をマッチングを利用して見つけました。
事業転換や新たな事業展開についての事例
日本酒専門メディア「SAKETIMES(サケタイムズ)」を運営している株式会社Clearが、1965年創業の老舗酒屋「有限会社川勇商店」を小規模M&Aで買収した事例も話題になりました。
株式会社Clearは自社でメディア運営を行い、日本酒に特化したベンチャー企業です。
専門メディアも好調で「酒類小売業免許」の取得を目的としてM&Aを敢行したといわれています。
元々販売に興味を持っていた同社では「通信販売酒類小売業免許」は取得したものの、こちらの免許ではECでの販売に限定され課税移出数量・品目・地域の制限があります。
日本酒業界では大手、準大手に位置する蔵の酒を販売対象とすることができないので、成約を受けずに魅力的な日本酒を販売する方法として小規模M&Aを採用し「酒類小売業免許」を取得している企業を買収した実例になります。
同様に、2014年にはAmazonが酒類のネット販売をスタートする際に「酒類小売業免許」を持つ酒販店を買収しています。
関連する記事について

個人向け小規模M&Aの探し方
近年は個人でもM&Aにて企業や事業の売買を行うことが増えています。
少額でM&Aができることもありサラリーマンが独立起業をする際に活用されるケースが目立ちます。
しかし自身の人脈や交友関係の中だけでは良いM&A案件を見つけるにも限界があります。
ここでは効率の良く個人が小規模M&A案件を探せる方法を解説します。
仲介会社を利用する
業界特化型のM&A仲介会社の利用も一つの手段として挙げられます。
さらに小規模M&Aを専門に行う仲介企業も近年は増えてきています。
個人であっても、よりマッチングしやすい案件の紹介が期待できます。
特にM&A自体が初めての場合には専門家のアドバイスはとても重要になります。
マッチングサイトを利用する
マッチングサイトを利用してM&A案件を見つける方法もあります。
あくまでもサイト運営側はM&A案件の提供のみであり価格交渉や手続きをしてくれるわけではないので注意が必要です。
そのため手数料や利用料は仲介会社やアドバイザーを利用するよりも安価にすむメリットはあります。
企業と直接交渉ができる、法務や税務に関する知識がある方であればオススメできる手法です。
士業に相談する
小規模M&Aであっても税務や会計、法務に関しては専門家の力が必要になります。
手続きも煩雑であり専門知識を要するので税理士・公認会計士・弁護士などに条件交渉や契約手続きを相談するのは有効です。
商工会議所に相談する
商工会議所は各地方にあり、地域の小規模事業者の支援を行う機関です。
商工会議所内には事業承継に関して相談できる機関があり、互いの事業や地域の発展を目的としています。
地元企業のネットワーク構築に対しても情報を保有しているので、相談することで地域内での適切な企業やM&A案件を紹介してくれます。
しかし、全国すべての商工会議所で相談が可能なわけではなく手続き自体は相談できないなど注意が必要です。
まとめ
中小規模や個人を対象とした小規模M&Aの市場は活況です。
補助金や支援サービスも拡充されている傾向にあるので、今後もより身近なビジネス手法として採用されていくと予想されます。
しかし身近なサービスとして活用できるのは、しっかりと注意点や特徴をしったうえでのことになります。
法律や財務の知識も必要なので円滑に小規模M&Aを実施する際には、専門家へ相談することから始めましょう。