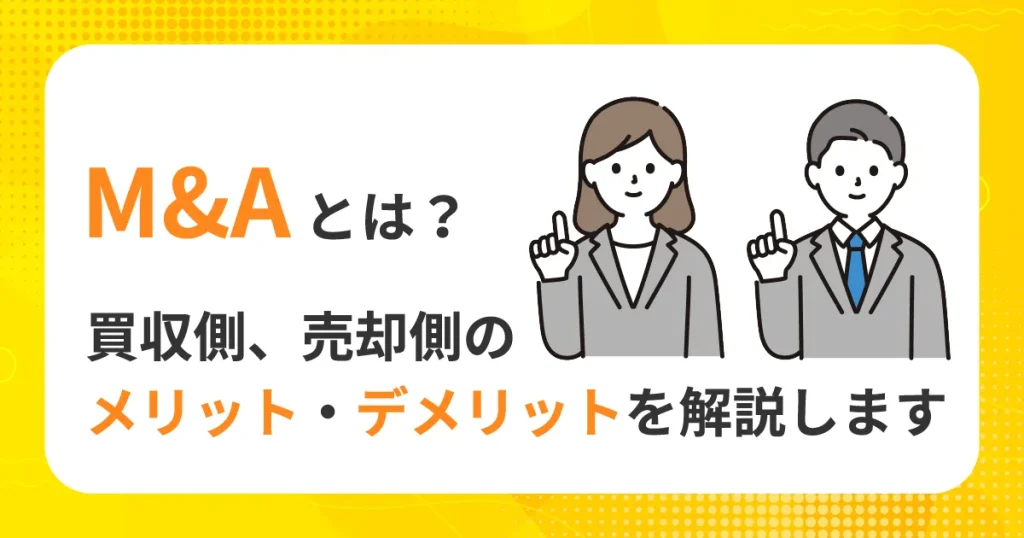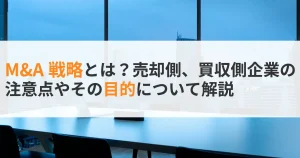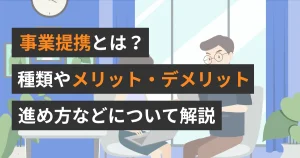M&Aとは?買収側、売却側のメリット・デメリットを解説します。
近年、日本国内において社会問題となっているのが事業後継者の不足問題です。
実に日本企業の6割以上が後継者の不足に悩んでいるのです。
後継者がいなければ会社は廃業となってしまいますが、そんな時の解決策としてM&Aが注目を集めています。
M&Aとは?
M&Aの「M」はMergers(合併)の頭文字、「A」はAcquisitions(買収)の頭文字であり、
M&Aとは、企業における合併買収を意味します。2つの企業が合併して1社になる、一方の企業がもう一方の企業を買収して一つになることを指しています。
この記事ではM&Aにおける目的やメリット・デメリットを買収側の企業、売却側の企業それぞれの視点から解説します。
↓こちらの記事もおすすめ!
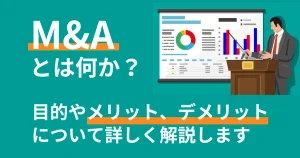
M&Aとは何か?目的やメリット、デメリットについて詳しく解説します。
M&Aの目的
M&Aを実施する目的は企業によって様々です。譲受け企業、譲渡企業別にM&Aの目的を見てみましょう。
買収(譲受け)側のM&Aの目的
譲受け企業とは買収する側の企業です。買収する側の目的には、新規事業への参入や自社の既存事業をスケールメリットによって拡大強化するなどがあります。
買収する目的
新規事業への参入を検討している
新規事業への参入を検討している場合にM&Aをするケースです。
自社にはない技術やノウハウ、人材といった経営リソースを既に保持している企業を買収することで、効率よく新規の市場に参入を果たし効率よくビジネスを展開することができます。
既存の事業を強化するため
新規事業ではなく、自社の事業と同カテゴリーでもM&Aは活用されています。買収をすることでシナジーを得られる企業であれば、自社の既存企業を強化することができます。
自社サービスと関連性がある企業であれば、更に優秀な人材の獲得や販売チャネルの強化に繋がります。
企業規模拡大によるスケールメリットを獲得するため
M&Aをすることで相手側企業の資産や従業員を自社に譲り受けます。そうすることで既存事業の拡大を図ります。
事業の拡大により認知度の向上、交渉力の強化などスケールメリットを得ることが可能です。
売却(譲渡)側のM&Aの目的
一方、譲渡側によるM&Aの目的にはどんなものがあるのでしょうか。
売却する目的
①後継者問題の解決、事業承継
冒頭にも記載しましたが、現在の日本企業においては後継者が不足している問題が社会問題となっています。
帝国データバンク調査
帝国データバンクの調査によれば、2021年の全国・全業種約26万6000社における後継者動向は、後継者が「いない」、または「未定」とした企業が16万社に上った。
この結果、全国の後継者不在率は61.5%となり、20年の不在率65.1%から3.6ptの改善、4年連続で不在率が低下し、調査を開始した11年以降で最低となったと報告されており、特に中小企業において後継者問題は深刻化しています。
後継者がいなければ会社は廃業してしまいます。M&Aを実施することで後継企業に既存事業を引き継いでもらい、オーナーは創業者利益を獲得してリタイアする流れが一般的になってきています。
②従業員、ノウハウの承継
①に関連して、これまで会社が蓄積してきた技術やノウハウも倒産や廃業してしまえばそこで潰えてしまいます。また企業に属していた従業員も同様です。
会社がなくなってしまえば技術は無となり、従業員は職を失うだけです。M&Aを実施することで従業員は新しい職を得ることができ、技術やノウハウも新しい環境に引き継がれていくことができるのです。
③事業の整理
複数の事業を展開してきたが思うように経営リソースを配分できず、想定していた収益が得られなかった企業がM&Aで不採算事業を売却するケースがあります。
業績不振が続いていた部門を自社から切り離すことで根幹事業に集中できるメリットがM&Aにはあります。
M&Aのメリット
効率的なビジネスを後押ししてくれるM&Aは合理的で、譲受け側、譲渡側双方にとってシナジーとメリットが享受できます。
買収(譲受け)側のメリット
M&Aには狭義から広義なものまでその手法は様々です。既に完成している企業を買収することで得られるメリットには下記があります。
スケールメリット
M&Aでは売却側企業の資産や不動産などの有形資産を獲得します。さらには技術やノウハウといった無形の資産も得られることは大きなメリットです。
M&Aによって事業が拡大することで、様々な場面でのスケールメリットが得られます。
企業が大きくなることで取引量が増加すれば、取引先に対しての交渉力は強化され、大量注文による仕入れコストの削減に繋がります。メーカーにおいては設備の稼働率の向上、小売業やサービス業界であれば知名度やブランディングの成長に大きく寄与します。
チャネルの増加
企業のおける経済成長は、どの企業においても大きな課題となっています。しかし、新しい販売チャネルや流通チャネルを獲得することは困難なものです。
その点M&Aであれば売却側が構築した販売チャネルや流通チャネル、取引先を一気に獲得して事業の拡大を図ることが可能です。
事業の多角化
企業おける事業環境は厳しさを増しています。事業の成長を実現しなければ収益は得られず、収益の安定化を図らなければ事業の存続はより困難になっていきます。
企業において収益の増大、安定化を目指すためにM&Aで事業を多角化することは企業成長に対する手法としても有効です。
自社とは異なる分野の事業を有する買取対象企業を取り込むことで、新規事業への参入も効率よくスピーディーにおこない、バリューチェーンの拡大に繋がります。
売却(譲渡)側のメリット
M&Aによって事業を売却する側においてもメリットは複数あります。
廃業コストの削減
前述しましたが日本の中小企業、特に地方の企業においては後継者不足に悩む企業が全体の約6割を超えています。
中には黒字でありながら会社を畳み、一代で終わらしてしまう創業者も後と絶ちません。
事業の撤廃や廃業を考えている企業も多いですが、廃業をするにも何かとコストは発生します。
会社備品の処分や店舗の原状復帰などのコストも決して安くはありません。その様な場合にM&Aでの事業売却が叶えば、廃業コストは一切かからないというメリットがあります。
事業の承継による従業員やノウハウの継続
廃業コストの削減に関連して自分の代で事業を終わらしたいと考えていても、雇用している従業員の就労先が確保できないままでは廃業できないと思っている経営者も多くいます。
また廃業することでそれまで蓄積された技術やノウハウは雲散霧消となってしまいます。M&Aであれば店舗や従業員などの有形資産、技術やノウハウといった無形の資産を全て含めて買取対象企業へと引き継ぐことが可能です。
事業拡大
M&Aにおいては売却企業よりも、買取企業の方が企業の規模も大きく保有している資産も大きいもの。
自社よりもステータスに優れている企業にM&Aされることは、自社のスケールでは実現できなかった企業成長を達成できるともいえます。
既に多くのインフラや資産を持っている優良企業に属することで、海外展開や新規事業への参入、サービスや製品の認知度の向上などが見込めます。
M&Aのデメリット
M&Aには様々なメリットがある反面、デメリットも存在しています。2社が一つになることでのシナジーを得られないデメリットにはどんなものがあるのでしょうか。
買収(譲受け)側のデメリット
M&Aにおいてデメリットを生じやすく留意すべきポイントには下記があります。
企業文化や社風によるズレが生じる
それまで企業文化が異なる2社が1社に統合される時に、社風の違いから従業員間での精神的な溝が出来たり派閥が出来てしまい対立に至る事例はM&Aにおいてはよくあります。
M&Aでのシナジー創出を目論んでいたものの、想定した結果にならない自体は非常にもったいないので留意が必要です。
簿外債務、偶発債務などの財務リスク
M&A後に、貸借対照表には計上されていない債務「簿外債務」が発覚するケースもM&Aにはよく見かけます。
また現実には発生していないが将来的に、保証先の不履行など一定条件後に発生が確定する債務「偶発債務」などの財務リスクはM&Aにおいて発生がしやすく、M&Aの実施前に買取先企業の財務状況をしっかりと調査する必要があります。
人材やノウハウの流出
優秀な人材獲得を目的の一つとしてM&Aの実施が行われた場合には、事前に該当する人材や優秀なキーパーソンとコンタクトを取り、買収後の処遇、待遇、将来のビジョンの共有をしておく必要があります。
M&Aによって組織派閥や対立が起こり、社外への人材流出リスクは高まります。優秀な人材の確保には十分留意しておくことが重要です。
売却(譲渡)側のデメリット
譲渡側に想定されるデメリットには下記があります。
想定して金額での売却ができない
買収側の企業からすると、M&Aでは将来的にどれだけの収益を見込めるかが重要になります。
売却側からすると自社にどれだけの企業価値があるかを把握して客観視できるかはM&Aのカギになります。
現在の収支状況が好調であっても将来的に成長や価値が見込めないと判断されれば、想定していた金額を下回る条件を提示されます。最悪の場合には買い手が現れない事態もありえます。
買取側による雇用条件の変更
M&Aが実施され2社が統合された後に雇用条件や労働条件の変更がなされるケースもあります。
譲受企業による雇用や労働条件の変更に対して以前との条件と大きく乖離するようであれば、譲渡企業から来た従業員のモチベーション低下による社外への流出、離職のリスクは高まります。
取引先との関係悪化
M&A後にそれまでの契約条件や取引条件の変更、担当者の異動や離職があった場合には取引先の心象も変わり関係が悪化することも想定されます。
以前までは良好な関係が築けていたとしても、M&Aにより社内体制や組織の変更に伴って取引先との関係が解消される例も多く見受けられます。
M&A成功のために重要なこと
M&Aを成功に導くための重要なポイント
組み合わせ
条件交渉
アフターM&Aマネジメント
①組合せ
中堅企業、中小企業においてM&Aでの候補企業の選択肢は非常に多いといえます。その豊富な選択肢の中で優良なマッチングとされるのは下記3つのポイントをクリアしていることです。
・シナジーの創出がしやすい
・経営リソースを相互補完している
・経営文化が似ている、共通していることが多い
逆にこの3つのポイントに相反する企業同士のM&Aは想定していた効果が得られない、シナジーが薄い結果に終わることも多くあります。
②条件交渉等のあり方(Execution)
M&Aにおいては、エグゼキューション(execution)が重要とされています。
エグゼキューションは実施、実行、執行を意味し、ここではM&Aにおける条件交渉などのあり方を指します。
シナジーを生みやすい企業マッチングだとしても買取り側の企業が尊大な態度で売却企業に対すれば統合しても感情的なシコリを残します。また売り手側の企業実態や事業の将来性に見合わない価格でのM&Aも現実的ではありません。
③アフターM&Aマネジメント
M&Aにおいては企業の買収や合併が目的ではありません。あくまでもM&Aは手段であり、目的は企業成長や事業規模の拡大にあります。M&Aの成功か否かの判断はM&A成立後の経営次第といっても過言ではありません。
M&Aの成否を握るのは統合のプロセスであるPMI(ポスト・マージャー・インテグレーション/Post Merger Integration)とも言われ、最大効果を発揮するためには買収企業から売却企業へ派遣する人材の選定や売り手側人材のモチベーション維持などが重要です。
まとめ
M&Aには、譲受け企業、譲渡企業双方においてメリットが得られる経営手法です。
しかし一方で売り手にも買い手にもそれ相応のリスクやデメリットは存在します。
未然にリスクを回避するためには、あらかじめM&Aで発生するデメリットやリスクを十分に把握し、解決策までを考慮して実行に移すことが重要です。
M&Aは一社だけでは成立しません。成功するM&Aには自社に見合った適切なパートナー企業が必要ですし、ベストなタイミングを見図ることがポイントになります。