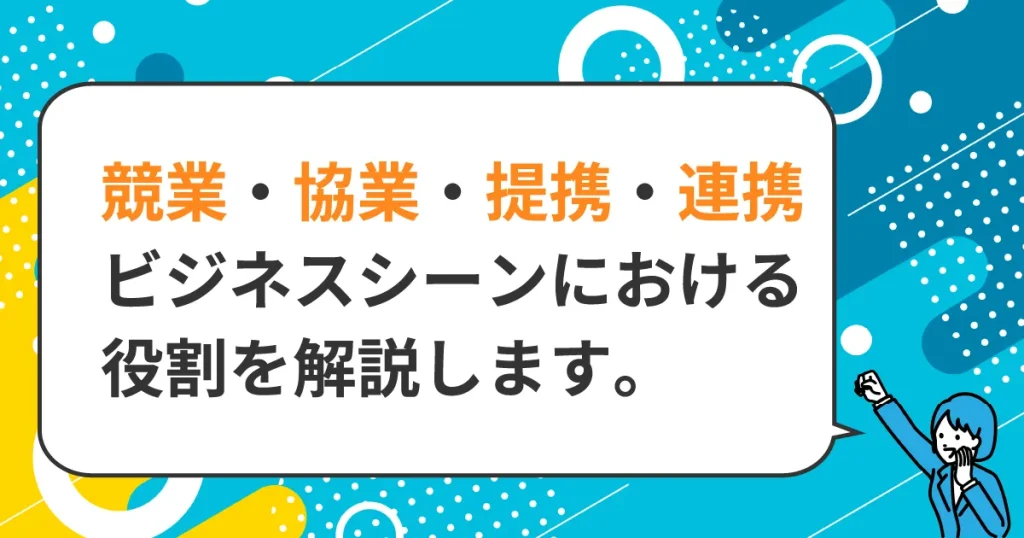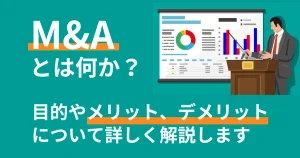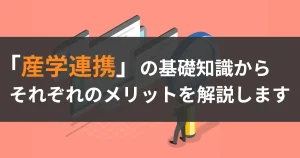競業・協業・提携・連携、ビジネスシーンにおける役割を解説します。
ビジネスシーンにおける協業のあり方にはどのようなものがあるでしょうか。
人の生き方、働き方が多様化するに従って、会社の事業展開に柔軟さが必要になってきました。今回は「協業」「競業」「提携」「連携」、それぞれの意味や協業をはじめるときに気をつけるべき点を紹介します。
競業・協業・提携・連携の違いについて
企業同士が協力しあってビジネスを展開する仕組みには幾つかパターンがあります。
「A社とB社による業務提携が結ばれた」「C社の新規事業はD社と連携して行われる」といったニュースを目にする機会も多くありますが、意味を混同してしまいがちです。
この記事ではビジネスにおいて混同しやすい「競業」、「協業」、「提携」、「連携」の意味と違いを解説します。
競業とは
「競業」とは文字通り「営業上の競争」をすることです。同じジャンルの業種において、複数の企業や個人が営業活動で競い合う状態を指します。後述する「協業」とは同じ「きょうぎょう」読みですが、意味は全く違います。
ビジネスにおいて「競業」という言葉は、「競業避止義務」に関する記載やニュースで取り上げられます。
「競業避止義務」とは従業員が自社と同業の他企業で働くことや、個人で自社と競合する内容のビジネスを行うことを制限する義務のことを指します。
また企業の重役や役員の場合は会社法によって「競業避止義務」が規定されていることが一般的です。
協業とは
協業の本来の意味は「生産過程において複数の労働者が集まり協力して作業をすること」を指しています。
現代のビジネスにおける「協業」とは、企業と企業が提携して事業を展開し、互いに不足している経営リソースを補い合うことでシナジーを得ることを目的にしています。
競業は広義の意味で「異なる企業同士が協力し合ってビジネスを展開する」ことであり、種類も様々です。
「協業」における有名なスタイルには「業務提携」「資本提携」があるので、それらを総括しているのが「協業」と考えると良いでしょう。また「アライアンス」や「同盟」といわれる事業スタイルも「協業」にあたります。
提携とは
本来の「提携」の意味は「互いに助け合うこと、協力し合うこと」であり、ビジネスにおける「提携」は前述した「協業」と大まかな意味は同じです。有名な「提携」には「業務提携」、「資本提携」があり分野毎に様々な種類を持ちます。
ちなみに「業務提携」の目的は、不足している経営リソースを補い合って競争力の強化や新規事業の成功を目指すこちにあります。業務提携には資本(株式)の移動がないので、解消するのもライトにできるのが特徴です。
「資本提携」は、資本(株式)の移動や譲渡があり、出資をする側と出資をされる側で一定の主従関係が発生します。経営権には影響しないレベルの資本の異動なので企業の独率性は保たれます。
連携とは
「連携」には「複数の人間や組織が同じ目的のもとに連絡して協力しあい物事を進める」という意味があり、広義の意味では「提携」も「連携)に含まれます。
前述した「業務提携」には明確な定義がありますが、「業務連携」となると辞書的な定義を持ちません。
「業務提携」は異なる企業同士の取り組みであること、契約が締結されるなどビジネスとしてより解像度が高く具体的でありますが、「業務連携」は自社内の異なる部署間での連携を指す場合が一般的であり、「提携」よりも関係性は弱いとも取れます。
関連する記事
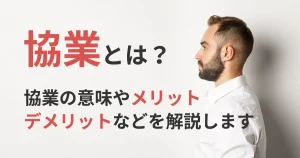
企業が協業をはじめるときに気をつけるべきこと

協業は、企業間に不足しているリソースを互いに補ってシナジーを得られる有効な経営スタイルです。
自社が協業を行う際には以下のポイントに気を付けるよう意識しましょう。
協業自体を目的にしない
「協業」は自社の強みとパートナー企業の強みを合わせることで新たなシナジーを創出する「手段」であることを忘れてはいけません。
あくまでも手段であって協業することが目的ではありません。最終的な目的は「新しい価値の創出」であることを念頭において行いましょう。
いつでもやめれる覚悟を持つ
ビジネス上の目的やベクトルが同じであったり、双方にメリットが発生している時は「協業」に意味はありますが、メリットや結果が伴っていない場合には協業関係を続ける意味は希薄になります。
惰性で続けている場合には、悪くすると双方にデメリットが発生しているかもしれません。その様な時は思い切ってパートナー企業との関係を解消する選択をしましょう。
協業でビジネスを成功させるためのポイント

「協業」によって良い結果を残すためには下記のポイントを意識することが必要不可欠です。
協業する目的を明確にする
「協業」を成功に導くには条件や目的が明確になっていることが大切です。
前述した通り「協業」自体が目的になってしまうと、協業相手に対して求めるものがあやふやになり事業計画もブレてしまいます。双方にとってメリットが発生し新しい価値を創造できなければ「協業」を行う意味もありません。
お互いの強みをよく把握しておく
「協業」するにあたっては事前に自社の強みを把握しておくことが大切です。同様に自社の弱みや不足している経営リソースを明確にしておくことも重要です。自社に不足しているピースが相手企業の強みでないと「協業」をする意味はありません。
「協業」においてはパートナーと強みや弱みが被らないようにしましょう。
まとめ|ビジネスにおける協業のあり方を理解しよう
ビジネス用語である「競業」「協業」「提携」「連携」の意味を解説してきました。ビジネスシーンにおいてはよく似た単語が頻出しますが、本来の目的を理解して使うべきタイミングで使用することが大事です。
また「協業」自体は不足している経営リソースを補えるメリットがあり効率よく事業展開ができますが、目的が不明瞭であったり事前の調査が不十分なままに行うと成功には程遠い結果になってしまいます。
最悪なケースでは企業間のトラブルや訴訟にも発展してしまいますので、始める前こそ入念な準備を心がけましょう。