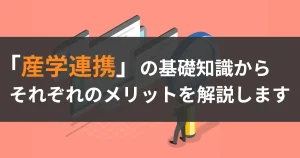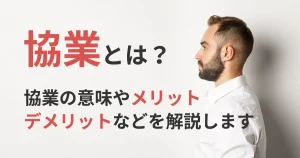アウトソーシング事業とはどのようなものかについて解説します。
近年、採用コストの削減や業務の品質向上を目的にアウトソーシングを行うことが一般的になりました。
元々は自社の開発業務やシステム運用の部分的な業務を社外に委託することを「アウトソーシング」と呼んでいましたが、現在では開発分野に関わらず、経理、総務、生産、物流など様々な分野においてアウトソーシングは行われてます。
この記事では、アウトソーシングの基礎的な解説からメリット・デメリットを掘り下げていきます。
アウトソーシング事業とは?

アウトソーシング(Outsourcing)は、外部を意味する「アウト」に資源利用を意味する「ソーシング」がくっついた和製英語です。
ビジネスにおけるアウトソーシングは「外部に仕事を委託する」という意味を持ちますが、原語の意味は「外部の資源やサービスを活用する」といった意味合いが強いかもしれません。
元々アウトソーシングが誕生したのは1960年代のアメリカであり、経営における人件費、設備投資費の高騰が原因とされています。特にITの分野においては設備投資費が高額になりやすい傾向があったので1990年代に入るとアウトソーシングは同分野において一般的な経営手法となっていきました。
更には世界的なカメラ用品メーカーのコダックが業績の低迷から生産部門の近代化を図るべく情報システムの一端をIBMに委託したことで、「アウトソーシング」という用語は有名になりました。
インソースとアウトソース
アウトソーシングが外部への委託を意味するのであれば、逆に業務の内製化を意味するのが「インソーシング」です。自社の業務領域の中でどこからどこまでがインソースでおこない、どこをアウトソースで賄うかの「ソーシング戦略」は非常に重要です。
インソースとアウトソースの区分けを考えるときには下記3つの分類があります。
1.専門業務 or 一般業務
専門性の高い業務や自社でノウハウを持っている業務であればインソースとして内製で業務を行い、単純作業や専門性が高くない一般業務をアウトソースすることで業務の効率化を実現できます。
2.コア業務 or ノンコア業務
コア業務とは「事業の根幹を成す業務、主幹的な業務」を指します。分かりやすくいえば利益に直結する業務であり、事業戦略、経営企画、マーケティング、営業、人事採用などがコア業務にあたります。またコア業務には経営的であり高度な判断を求められるケースも多く、外部に委託し辛い側面を持ちます。一方ノンコア業務とは、直接的に利益には結びつかないもののコア業務のサポート的な業務全般を指し、定型的で高度な判断が必要がないのでシステム化できてアウトソーシングに向いています。
3.戦略的業務 or 非戦略的業務
2と重複しますが、戦略的業務とは事業戦略、経営企画、マーケティング、営業などの業務。戦略的業務はインソースでおこない、単純作業の非戦略的業務をアウトソーシングする流れが一般的ですが、業種によっては非戦略業務も専門性が高い場合もあるので①②と併せて複合的な判断が必要です。
コ・ソーシング
コ・ソーシング(co-sourcing)は、依頼した企業と受託した企業が対等の立場を取って共同で業務にあたり、利益は分派する契約形態を指します。
コ・ソーシングの「co」は「共に」を意味する接頭語であり、発注する側の企業の人間も一緒に業務にあたります。なぜその様な形態をとるかといえば、一般的なアウトソーシングでは業務全般を外部委託してしまい自社にノウハウや情報が蓄積しないからです。
発注企業側には一緒に働くことで受託側企業が持つ専門性の高い技術、ノウハウ、情報などを自社に取り入れ、スタッフのスキルアップに繋げられるメリットを持ちます。受託企業には事業の成功によっては追加の利益が得られるメリットがあります。
アウトソーシングのメリット

アウトソーシングを活用することで様々なメリットが得られます。大きなメリットとしては下記の四つが挙げられます。
業務の処理速度と品質を高める
アウトソーシングを専門的に受託している業者は、専門性の高い技術、知識、ノウハウを持っています。
またアウトソーシングの受託を様々なクライアントから受けていることも多いため自社で業務を行うよりも、業者を活用することで業務の処理速度と品質を高めることが可能です。
自社の組織の肥大化を防ぐ
多くの企業は歴史を重ねるごとに組織が肥大化していきます。肥大化した組織は構造が複雑化していき、それによって元々備えていた活力が減退していきます。組織の肥大化とは、企業に潜む不可逆性であり、避けられない事態なのです。
自然と大きくなることはあっても、自然と規模が縮小することがないのが会社組織の宿命でもあります。
組織の肥大化の改善策としてもアウトソーシングは有効な手段です。アウトソースする部門や業務先を分社化して組織のスリム化を図り、人員の最適化、及びコストの削減を実現します。
人件費を抑えることができる
組織内の人件費は固定費ですが、業務の委託費用は企業の売上に応じて変動します。アウトソーシングを行わず業務を内製で行う場合には、売上げが大小に関わらず人件費は変動しません。
売上げが少ない、売上予算達成が難しい場合には人件費率が上がり利益を圧迫します。一方、アウトソーシングであれば売上げの増減に応じて委託費用は変動できるのは大きなメリットでしょう。
また、比較的難易度の低い業務をアウトソーシングすることは、新規に正社員を雇用する経済的コスト、雇用した社員を教育する時間的コストの削減にもつながり効率の良い人員マネジメントを可能にします。
「自分でないとできないこと」に集中できる
中小企業においては単純作業でありながらもボリュームがあって工数がかかる業務が多いものです。特にPCで行う定型作業や事務作業に貴重なリソースを割くのは非効率的です。
それでなくても少子高齢化から生産年齢人口が大きく減少していく中で、正社員に単純作業をさせてしまうことは人的リソースの無駄遣いともいえます。
単純作業や誰でもできる内容の業務はアウトソーシングをして、クリエイティブで生産性の高い業務に集中することは業務効率化にも大きく貢献するものです。
アウトソーシングのデメリット

アウトソーシングにはメリットだけではありません。デメリットもあるため導入においてはよく検討する必要があります。
社内にノウハウが蓄積されない
専門性の高い業務を外部に委託することで業務効率化を図れるというメリットがある一方、自社に業務のノウハウが蓄積されないというデメリットが存在します。
またアウトソーシングが常態化してしまうと業務プロセスがブラックボックス化してしまい、委託先の企業が倒産したりサービスから撤退した時に対応ができなくなる可能性もあります。アウトソーシングを検討している場合はその様なリスクを念頭においた運用が必要になります。
コストが高まるリスクがある
コスト削減を期待して導入を決めたアウトソーシングが逆にコストが高くなるケースもあります。
既に自社内で効率化されていた業務や、専門外のため業務委託費用の相場が分からない場合には通常のアウトソーシングよりも高い費用で委託してしまうことになります。
情報漏洩のリスクがある
機密性の高い業務をアウトソーシングする場合にはどうしても企業機密や個人情報を委託先企業と共有することになります。
発注側、委託側の企業が双方ともにセキュリティ対策を講じても情報漏洩のリスクは0にはなりません。
特に人事、カスタマーサポート、情報システムに関連した業務をアウトソースする場合には委託先の企業の選定は慎重におこなうべきです。
関連する記事

まとめ
アウトソーシングは有効に活用することで、人件費の削減や業務効率化に繋がります。
それらを実現するためにもアウトソーシングにおけるメリット・デメリットや特徴をよく理解した上で自社に導入することをお勧めします。