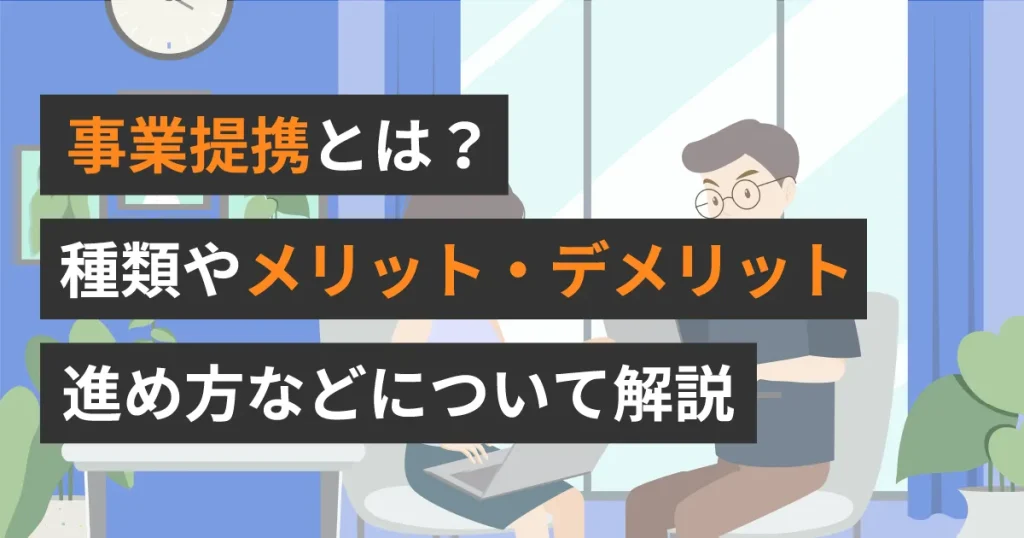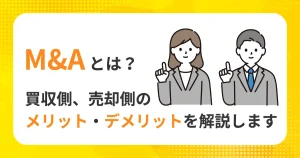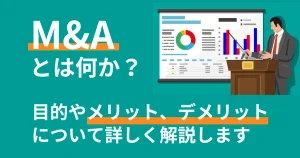事業提携とは?種類やメリット・デメリット、進め方などについて解説。
様々な業界でDX化が進み、これまで異分野同士であった業態で事業提携が行われるようになってきました。しかし事業提携の内実に詳しい人は、多くありません。
事業提携とはどのようなものなのでしょうか。この記事では、事業提携の種類やメリット・デメリット、進め方などについて解説していきます。
事業提携とは
事業提携とは、複数の企業が特定のジャンルにおいて事業遂行を行うための関係を結ぶことです。
同様に複数企業による吸収や合併を伴う事業遂行の対応にM&Aもあります。
似て非なる事業提携とM&Aどのような違いがあるのでしょうか。また事業提携における種類を解説します。
事業提携とM&Aの違い
M&Aは、企業の合併買収に伴い、買い手(譲受)企業が売り手(譲渡)企業の経営権を取得します。
事業提携も複数の企業が協力して事業の遂行をおこなうことは共通していますが、M&Aの場合には売却側の企業は、買収側企業の経営方針に基づいた行動が求められますが、事業提携の場合にはM&Aほどの縛りはなく契約の解消もライトに行えます。
経営の独立性が担保されているのは事業提携であり、事業提携とM&Aは経営の独立性においては似て非なるものであるといえるでしょう。
事業提携の種類
事業提携には、大きく分けて「生産提携」「販売提携」「技術提携」「資本提携」の4つがあります。
生産提携
生産提携とは、自社製品の生産、及び一部製造を対応できる企業に委託する形式の事業提携です。主に売上げが好調な企業において需要過多となり生産が追い付いていないケースに活用されます。
販売提携
販売提携とは、既に流通網や販売ルートを持っている企業に販売自体を委託すること。技術力や商品力はあるものの販売ルートが確立できてない場合に活用します。販売代理店制度やフランチャイズ制度などの手法が販売提携にあたります。
技術提携
技術提携には、企業が相互に人材や技術を提供し合って特定の技術を開発する「共同開発」と、技術を持たない企業に対して、持っている企業が技術を提供し生産活動にも協力する「技術供与」があります。
資本提携
資本提携とは、提携を行う企業同士が相互に資本面でも協力しあう手法です。一方の企業が相手方に資本を拠出する形式と、相互に株式を保有する形式があります。
株式の取得方式には、一方が所有する株を買手企業に売買して譲渡する「株式譲渡」と、特定の第三者に新株を割り当てることで資金調達を行う「第三者割当増資」があります。
資本(株式)の移動や譲渡があり、出資をする側と出資をされる側で一定の主従関係が発生するので資本提携は広義のM&Aでもあります。
しかしながら経営権には影響しないレベルでの資本の異動なので企業の独率性は保たれます。
事業提携のメリット・デメリット
事業提携におけるメリットやデメリットをそれぞれ解説します。
事業提携のメリット
事業提携を行うメリットには下記の3つがあります。
機会損失を防ぐ
生産提携の場合、自社の事業が好調で生産が追い付かないために実施されるケースがほとんどです。このように提携を有効に活用することで販売機会の損失を防ぎ、本来あるべき収益を獲得することができます。また受託した企業においても工場施設の稼働率を向上させて自社での生産量もアップすることができます。
市場への参入スピードを早める
新商品の開発や新規市場への参入を検討しているが販売能力が不足している場合には、販売提携で販売手法や流通網を既に持っている企業のリソースを有効活用することで市場への参入スピードを早めることができます。
技術開発リスクの分散
相互に技術を持ち寄って共同での開発をおこなう場合には、高度な技術の開発が実現できるメリットがあります。新規の技術開発のスピードが向上することは、業界内での技術競争から抜け出しアドバンテージを得ると共に、技術開発におけるコストも複数企業で分散できるので一社での技術開発よりもリスクを回避できるメリットがあります。
事業提携のデメリット
一方、事業提携を行うデメリットには大きく下記の3つがあります。
生産ノウハウの社外流出リスク
生産を外部企業に委託する場合には、どうしても生産に関する情報を共有する必要があります。機密性の高い情報の漏洩やノウハウの社外流出リスクはどうしてもつきまといます。
マーケティングや経営方針の不一致
販売のノウハウやリソースが自社に不足しているからと、提携企業へ販売を丸投げしてしまうと本来のターゲットから外れたユーザーへアプローチしてしまったり、マーケティング戦略においてブレが生じてしまったりと、委託側と受託側でズレや方針への不一致が発生してしまいます。自社のマーケティング方針と相容れない販売戦略では、利益の最適化が見込めないリスクが生じてしまいます。提携に際してはマーケティング方針との整合性を失わない契約の締結が必須となります。
一社による利益の独占
共同の技術開発を目的とした提携には、委託先の企業が開発した技術を活用して得た利益を独占してしまうケースも見られます。技術を開発した後の生産計画や利益の分配などを、相互にきっちりと定めた上で契約を取り交わしトラブルへの発展を回避しましょう。
事業提携の進め方
事業提携の進め方は下記の様なフローで行われることが一般的です。
step1:提携目的の明確化
step2:提携交渉先の確保
step3:事業提携契約の締結
step4:事業提携契約締結後の対応
こちらでは事業提携の進め方を順番に解説します。
提携目的の明確化
事業提携だけでなく交渉時に目的が明確になっていないと、想定していない方向に進んでしまうケースはビジネスには多々あります。
事業提携をスムーズに行うためにも事前に自社の強みや方向性、事業提携における「目的」をしっかりと整理する必要があります。
自社の成長の為に必要な事業提携ですが、提携パートナーとなる企業にもメリットがなければ成立しません。自社にとってもパートナー企業にとっても相互にメリットがどの様に発生するかを明確にしましょう。
提携交渉先の確保
事業提携における目的をしっかりと認識した上で提携する企業の選定に入ります。
提携先を見つけて事業提携への合意を得る為の流れは以下の通りです。
・事業提携のメリット提携先を探す
・事業提携のメリット公的支援機関からの紹介、及び公的支援機関のビジネスマッチングサイトを利用する
・事業提携のメリット金融機関からの紹介を受ける
・事業提携のメリット展示会やエキスポを利用する民間のビジネス支援サービスやコンサルティングからの紹介を受ける など
提携先企業を見つけるためには複数ある情報経路から企業情報を検索し、業務提携先に見合う企業を選定します。企業情報を得るための機関やルートには下記があります。
基本合意契約の締結
事業提携先の企業を選定した後には、相手先企業への打診、内容のすり合わせを行ったうえで「基本的合意契約書」を取り交わすことが一般的です。また双方の企業情報の外部流出を防ぐために「秘密保持契約/NDA」を結ぶことも重要です。
事業提携契約の締結
基本的合意契約を締結した後には、本格的な交渉を持った上で 「事業提携契約」を取り交わします。
契約前準備
事業提携契約を締結する前に、双方の企業において事業計画内容の共有、事業の具体的な進め方、リスクの洗い出しなどを行います。契約の前には必ず双方の企業同意の元に意思の統一が必要になり、事前準備が確実な事業提携に繋がります。
事業提携の正式契約
事前準備を済ませ、本格的な事業提携の契約に進みます。双方の企業の意思の確認、及び企業トップ同士の面談を行ったうえで正式に事業提携契約を締結します。
事業提携契約締結後の対応
事業提携契約を取り交わすことが目的ではなく、双方の企業が事業提携を実現し互いにビジネスの上でメリットを享受することが本来の目的です。
事業提携契約を締結後の対応は極めて重要であり、定期的な進捗の共有や報告が求められます。また事業提携契約は長期に渡り実施していくものでもあり、トライ&エラーを繰り返し事業の最適化を目指します。
スタートアップが事業提携する目的
ここではスタートアップ企業にセグメントして事業提携を実施する目的を掘り下げていきます。
経営基盤の強化
スタートアップ企業において事業提携を選択するのは企業の成長戦略に対してとても有効な手段といえます。特にスタートアップ企業では新しい分野や課題に挑戦する傾向があり、従来の企業よりも直面する経営課題は多いもの。規模が小さく経営的なリソースが不足しがちなスタートアップ企業が、事業提携においてパートナー企業のリソースを有効に活用して効率よくビジネスを展開することは経営基盤の強化の為にも有効といえます。
事業価値の向上
商品開発や製品に自身を持っていても、スタートアップ企業では認知度やブランディングの力は不十分です。事業提携を行うことでパートナー企業の販売力や知名度を有効に活用し、自社の事業価値を向上させて認知度やサービス内容を世間に広く浸透させるメリットが得られます。
事業提携契約を締結するときのポイント
事業提携をスムーズに締結させ、契約後のトラブルやクレームを回避するために事業提携契約書に盛り込むポイントを幾つか説明します。
提携業務の内容と役割分担、責任の所在
事業提携における役割分担と責任の所在は事前にはっきりとさせておく必要があります。
・事業提携の効力はビジネスにおいてどの範囲まで有効か?
・どの業務をどちらの企業が担当するか?
・それぞれの企業が果たすべき責任はどの範囲か?
上記の内容が曖昧なままに事業提携がスタートしてしまい、想定していた結果にならなかった場合はトラブルやクレームに繋がることも考えられます。
最悪の場合は訴訟にまで発展してしまうケースもあるので業務内容と役割分担、責任の所在は事業提携契約に盛り込みトラブルへの発展を未然に防ぐ必要ぎましょう。
成果物や知的財産権などの帰属
事業提携のデメリットの項でも述べましたが、事業提携においては一方の企業が提携でえたノウハウや技術で得た利益を独占してしまう事例もあります。
利益の独占を未然に防ぐためにも、青果物や知的財産の権利がどちらの企業に規則するかを明確にしておきましょう。
秘密保持
事業提携におけるデメリットやリスクに、自社の機密性の高い企業情報やノウハウ、技術の流出や漏洩があります。
それらのリスクを未然に防ぐためにも、機密保持が及ぶ範囲と機関を事業提携契約に明記しておく必要があります。
費用の負担と収益の分配
事業提携に関わる費用負担や収益の分配などお金に関わる事項は企業間で揉めるリスクがあります。
紛争から訴訟になるケースもあるので、費用負担のルールと収益分配のルールを明確にした上で事業提携契約にも明記してトラブルを回避しておきましょう。
契約の解除
契約の解除に関しても企業間同士で紛争に発展しやすい特徴があります。
事業提携を行ったが想定した結果にならなかった、一方に義務違反があったなど契約解除に繋がる事例はいくつもあります。
こちらも契約破棄にかんしての紛争リスクを未然に防ぐためにも、どのようなケースであれば契約解除になるかを契約書に明記しておくことをお勧めします。
契約期間
正式な契約の締結をすることで契約書には法的な力が備わります。契約期間が長期になると契約を解除したいが違反になるため出来ず、無駄に長期間拘束されるリスクが発生してしまいます。
契約期間は1年程度とし、双方合意があれば都度更新する方式が一般的です。
まとめ|事業提携とは組織のシナジーを生む方法
今回は事業提携の種類や特徴から、事業提携契約が締結される一般的な流れを解説しました。
事業提携は、業務提携よりも企業同士によるシナジーを生む提携方法です。相互の強みやリソースを提供し合って強固な協力関係を築くことで、ビジネスにおける更なる成功や新規市場への参入に有効的です。
業務提携を検討してはいるが、初めてで不安を覚えるようであれば業務提携への専門知識を要する第三者の力を借りることで効果的な結果に結びつきます。
まずは自社の強みを確認し、提携する目的を定めるところから初めてみてはいかがでしょうか。