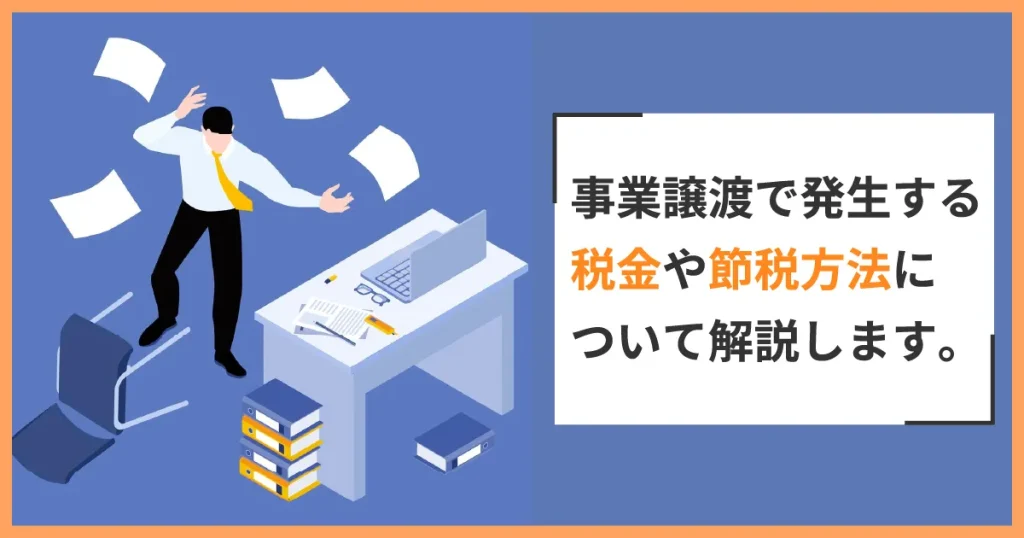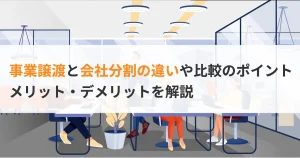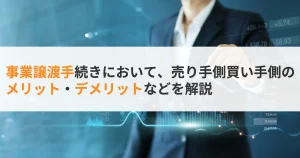事業譲渡で発生する税金や節税方法について解説します。
中堅中小企業のM&Aにおいて事業譲渡や株式譲渡、会社分割などはよく利用される手法ですが、それぞれに特徴やメリット・デメリットが違います。また課税される対象や税金の種類、税額も異なります。
この記事では事業譲渡で発生する税金や節税方法を解説します。
事業譲渡と税金
事業譲渡はM&Aにおいてポピュラーな手法の一つです。
自社の事業の一部、もしくは全てを譲渡するスキームを指します。
事業譲渡では事業に付随する資産(雇用、契約、流通、取引など)を譲渡することであり、売却側も買取側も基本的には法人格同士のやり取りとなります。
どちらも法人が当事者となるため事業譲渡で得た対価は会社が受け取り、法人税が発生します。
また事業譲渡には売却した事業及び資産に対して消費税率を掛けた消費税が発生します。
あくまでも「消費税課税対象資産」が含まれる場合であり非課税の資産を含む場合もあります。
さらに譲渡される資産の中に不動産がある場合には、買い手側企業に「登録免許税」や「不動産取得税」が課税されます。
| 事業譲渡で発生する税金 | ||
| 税金 | 計算式 | 備考 |
| 法人税 | 譲渡益の金額 = 譲渡価格 一(譲渡資産 - 譲渡負債)
税金 = (譲渡益 + 本業の利益) × 29.74% | |
| 消費税 | 課税資産 × 10% | 消費税課税対象資産が含まれる場合 |
| 登録免許税 | 土地の価格 × 15/1000 | 土地を譲り受ける場合 |
| 不動産取得税 | 不動産の価格 × 3/100 | 建物を譲り受ける場合 |
事業譲渡で発生する税金
事業譲渡では売り手、買い手共に税金が発生します。
ここでは売り手側企業、買い手側企業それぞれにどの様な税金が発生するかを見てみましょう。
売り手側の税金
事業譲渡において売り手側に発生する税金は法人税と消費税です。
法人税
売り手側には事業を売却して得た利益に対して課税されますが、売却益全てに対して課税されるわけではありません。
正確には、
「譲渡益の金額 = 譲渡価格 一(譲渡資産 - 譲渡負債)」
に対しての課税となります。
譲渡益がプラスであれば下記の税率を掛けたものが法人税となります。
「税金 = (譲渡益 + 本業の利益) × 29.74%」
譲渡益がマイナス、もしくは会社の収支状況が赤字であった場合にはマイナス分は法人税より差し引かれます。
消費税
事業譲渡において消費税は、譲渡(=売却)する資産に対して発生する税金になります。通常、消費税を負担するのは買い手側企業ですが、納付義務は売り手側にあります。
また消費税には課税対象になる資産と対象にならない資産があります。
消費税課税の対象となる資産
土地以外の有形固定資産、無形固定資産、棚卸資産、営業権(のれん代)
消費税非課税の代表的な資産
土地や有価証券、債権など
買い手側の税金
事業譲渡では買い手側が取得した資産に対しても税金が課せられます。
消費税
売り手側の税金で前述しましたが、譲り受ける資産に対して消費税が発生します。この場合には売り手側が買い手に対して金額を請求して納付します。
また消費税課税対象の資産と非課税対象の資産があるので、請求された金額の内訳詳細を精査した上で課税対象分の金額のみ支払う必要があります。
不動産取得税
譲り受ける資産の中に不動産が含まれる場合には、不動産取得税が課せられます。
不動産取得税の課税金額は、土地、家屋(住宅)であれば3%を取得した不動産の価格に掛けた金額になります(2024年3月31日まで)
登録免許税
登録免許税も土地や不動産取得に関連した税金です。
土地や建物の売買や贈与において所有権移転登記の申請時に発生する税金です。
事業譲渡において譲り受ける資産の中に土地や不動産が含まれている場合には、名義変更を行う義務が発生します。
それらの名義変更の為には所有権移転登記を行う必要があり、その際に支払い義務が発生します。
所有権移転登記にかかる登録免許税
取得する不動産の課税標準額に1.5%を掛けて計算した金額になります(2023年3月31日まで)
事業譲渡における消費税の注意点
事業譲渡において消費税が発生することは前述した通りです。
さらに事業譲渡における消費税の課税に関しては注意すべきポイントがいくつかあります。
のれん代の値上がり
上場していない中小企業の事業譲渡においては、譲渡価格にのれん代が含まれるのが一般的です。
のれん代とは?
企業が保有している無形固定資産を指し、その企業独自の技術力やブランド力、ノウハウなどが相当します。
そのため譲渡価格は「時価純資産額+のれん代」となり、消費税を算定する場合にはのれん代を上乗せしておく必要があります。
独自のブランド力や技術を持ちあわせている程のれん代は値が上がる傾向にあり、消費税額が多額になるケースもあります。
棚卸資産の不確実性
事業譲渡における消費税には棚卸資産も含まれます。
棚卸資産は「在庫」でもあるので、日々帳簿上での価格は変動します。
実際に事業譲渡を行なう日と棚卸資産の予測との乖離は起きやすく、棚卸資産を多く擁している企業との事業譲渡には注意が必要です。
消費税の引き上げ
現在(2022年1月)の消費税率は10%です。
日本に消費税が導入されたのは1989年であり約20年をかけて徐々に税率は上がってきました。
今後の社会情勢や景気によって消費税率が引き上げられる可能性も大いにあります。
事業譲渡を行うにあたっては消費税率の変動には大きく影響を受けてしまうので十分に留意しておく必要があります。
関連する記事

事業譲渡における節税の方法
事業譲渡においては売り手側、買い手側にそれぞれ異なる節税効果と特徴があります。
売り手側の節税
売り手側企業は事業譲渡で得た収益に対して法人税がかかります。
譲渡益が決算期まで残ったままにしておけばこの金額に対しての法人税を課せられてしまいます。法人税の減額を目的とした節税方法としては退職金の活用が挙げられます。
売り手企業の社長が事業譲渡を行った年度に退任し、その際に譲渡益を退職金に充てることで法人税を軽減し個人に所得を移動することができます。
退職金は経費であるので節税効果を得られます。
ただし、個人の所得税の税率は累進税率であるため、ある一定の金額を超えると法人税を支払うよりも高くなってしまう点には注意が必要です。
買い手側の節税
事業譲渡での買い手側企業には、移転する資産以上の営業権を高く買った分だけ、法人税の課税対象になる利益を5年間減らすことができます。
営業権とは、企業におけるブランドや技術、ノウハウ、人材などの無形資産です。目に見えない資産であり、「のれん」とも類似していますが賃貸貸借表上では数値としては計上されないという違いがあります。
買い手側にとってはインセンティブの性質を持つ節税効果といえるでしょう。
個人事業主が事業譲渡する場合の税金
事業譲渡は法人同士のM&A手法として説明してきましたが、近年では個人事業主が事業承継や投資目的で事業譲渡を活用するケースが増えてきました。
個人事業主が事業譲渡をする場合に課せられる税金について説明します。
相続と贈与の場合
個人事業主における事業譲渡の相手は主に子供や孫等の肉親であることが多く、その際に利用される代表的な事業譲渡の方法が相続と贈与です。
相続
相続による事業譲渡の場合には後継者に対して相続税が課せられます。
相続による基礎控除額は下記の通りで、
基礎控除額=(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)
法定相続人(配偶者や子供など)の数によって控除額が決まります。
相続税は基礎控除額の3,600万円を超えた額に対して発生します。
課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)= 課税遺産総額
譲り渡し側は亡くなる日までに確定申告を行って所得税を納めます。
贈与
贈与で事業譲渡を行う場合には、後継者に対して贈与税がかかります。
贈与性における基礎控除額は110万円であり、贈与した財産が110万円を超えた金額に対しての贈与税が発生します。
こちらも譲り渡し側は、贈与した日までに確定申告を行い所得税を納める必要があります。
事業譲渡の場合
個人事業主が、M&Aを活用して事業譲渡を行った場合には、売却側は確定申告を行い所得税の支払いが必要になります。
譲渡した資産の中に、土地や不動産が含まれている場合には譲渡所得税が発生します。
まとめ
事業譲渡における税額や税金の種類を解説をしてきました。
まとめると、事業譲渡で売り手側に課せられるのは法人税、買い手側に課せられるのは消費税、不動産取得税、登録免許税です。
M&Aは手法によって発生する税金の種類や税額が大きく異なります。
事業譲渡を検討している場合には他のM&A手法と比較して税務の点から見直してみてはいかがでしょうか。