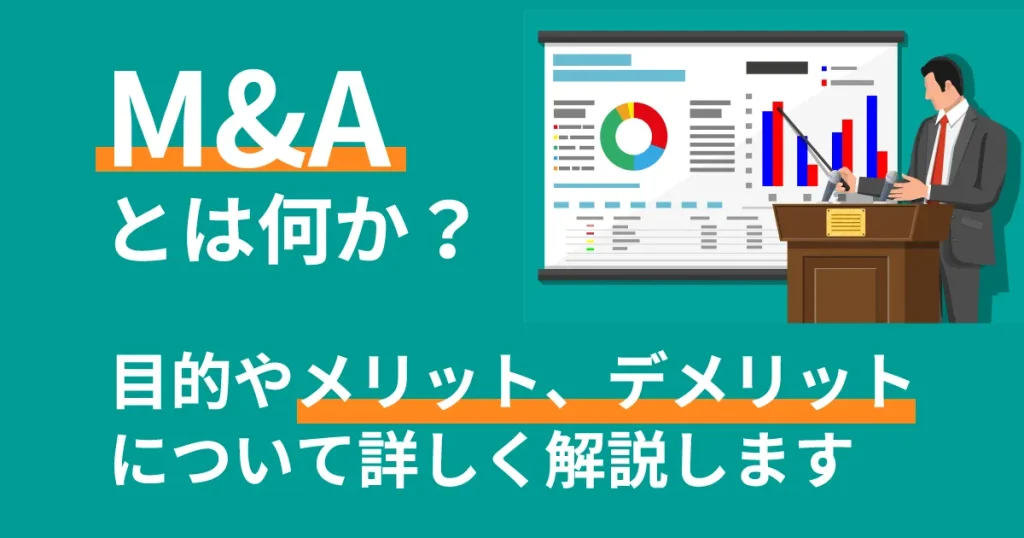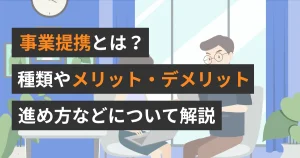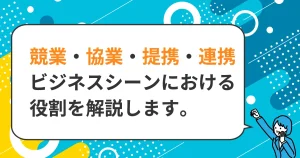M&Aとは何か?目的やメリット、デメリットについて詳しく解説します。
M&Aはどのような目的を元に行うべきなのでしょうか。
M&Aを成功させるポイントは、自社のポジションや買収側、売却側それぞれのメリット、今後の展望をしっかり見極めることです。
今回はM&Aの目的やメリット・デメリットについて解説します。
M&Aとは
M&Aとは『Mergers and Acquisitions』の略であり、Mergersは合併、Acquisitionsは買収を意味しています。つまりM&Aは「企業の合併買収、及び2つの企業が1つになる、企業の経営権を取得する」ことを意味しています。
一般的なM&Aの手法には買収・合併があり、この2つを狭義のM&Aとしています。広義のM&Aとして提携(業務提携・資本提携)も含みます。
買収
狭義のM&Aの一つである「買取」には、「株式譲渡」、「第三者割当増資」、「株式交換」、「株式移転」、「事業譲渡」といった手法があります。
| 株式譲渡 | 売り手オーナーが所有する株を、買手企業に譲渡することで会社を売買する方法。 |
| 第三者割当増資 | 株主であるか否かを問わず特定の第三者に新株を割り当てることで資金調達を行う方法。新株を引き受けた人物の議決権比率が高まることからM&Aでも活用される。 |
| 株式交換 | 完全子会社となる企業の株式の全てを、完全親会社となる企業に取得させる方法。M&Aの手法として一般的なスキームで1999年の旧商法改正時に導入されました。株式交換の実施においては資金の準備がいらないというメリットはあるが、売り手企業に対して買い手企業による完全支配権も発生する。 |
| 株式移転 | 1社ないし2社以上の株式会社が、新設の株式会社に対して発行済の全ての株式を取得させる方法。主にホールディングカンパニー設立の為に用いられるスキームであり、組織再編行為の一つである。 |
| 事業譲渡 | 会社における一部の事業、または全ての事業を第三者に売却(譲渡)する方法。 |
合併
こちらも狭義のM&Aである合併は、複数の企業を一つの法人としてまとめることを意味します。
「吸収合併」は消滅する予定の企業の権利義務を、存続する企業に吸収させて事業承継させる手法であり、「新設合併」は、新設した企業に合併予定企業の権利義務を承継させる手法です。
分割
M&Aの一つに「会社分割」があり、会社の全事業もしくは一部を他の企業に承継する手法です。買い手企業が売り手企業の事業資産を取得するので分割は買収に含まれ、会社分割には「吸収分割」と「新設分割」の2種類に分かれます。
吸収分割
企業における権利義務の全て、もしくは一部を分割して既存の企業に承継させる組織再編成の手法です。
新設分割
企業における権利義務の全て、もしくは一部を新設の法人に対して承継させる組織再編成の手法です。
M&Aの目的
近年、M&Aには事業承継、イグジット(投資回収)、個人の事業戦略など様々な目的があります。
ここでは買収企業側、売却企業側それぞれの立場でM&Aの目的を解説します。
買収(譲受け)側のM&Aの目的
買収(譲受け)側の目的には「新規事業への参入」、「既存事業の強化」、「事業の拡大」などが挙げられます。
新規事業参入
新たな市場への参入や新規事業の展開を検討している場合、M&Aによって既存の企業を買収する方が専門的な技術、人材、情報、ノウハウ等のリソースを効率よく獲得することができ、一から法人を設立するよりもコストの面で優れているメリットがあります。
軌道に乗っている企業を譲受ける場合にはリスクの軽減も見込めて効率の良い事業展開に繋がります。
既存事業強化
自社の事業を強化する目的でもM&Aは効果的です。自社事業とシナジーを得られそうな企業を買収し、生産性の向上や優秀な人材、新たな取引先を獲得できるメリットがあります。
スケールメリットの獲得
一般的に会社の規模が拡大することはブランディングや信用、交渉力にプラスに作用します。
材料の一括購入や大量仕入れによる原料の引き下げ、認知度のアップによる広告費の削減など。譲渡し企業の資産や経営リソースを取得することによるスケールメリットを見込んでM&Aをおこなう企業も増えています。
売却(譲渡)側のM&Aの目的
一方、売却企業側の目的には下記があります。
事業整理
M&Aでは企業における一部の事業を譲渡することも可能です。企業の規模が大きくなり幅広く経営活動していると業績が振るわず不採算事業になってしまうこと多々あります。
M&Aによって不採算事業を切り離し、主力の事業にリソースを集中することも経営判断の一つです。
事業承継のための後継者獲得
中小企業において後継者の獲得は重要な問題の一つ。事業の存続、承継を目的としたケースのM&Aも多く見受けられます。後継者が見つからずに廃業させるよりも、後継者を据えて創業者利益を得る方がオーナーにとってのメリットも得られます。
従業員やノウハウの承継
今や日本全体の社会問題でもある事業ノウハウの承継に関してもM&Aは効果的です。
これまで会社が培ってきた技術やノウハウを次世代に引き継ぐことができます。また廃業によって事業をたたんでしまった場合にはこれまで働いていた従業員は職を失うことになりますが、M&Aにより事業が承継されることは従業員の雇用も守ります。
M&Aのメリット
M&Aによるメリットを買収(譲受け)側、売却(譲渡)側、双方から見てみましょう。
買収(譲受け)側のメリット
M&Aにおいて譲受企業のメリットには、既存事業の拡大や新規事業への参入、事業展開の多角化などのメリットがあります。M&Aにより譲渡企業の資産、人材、取引先、流通網など経営におけるリソースを獲得することで、事業における成長スピードを加速させます。
売却(譲渡)側のメリット
譲渡側のメリットには、株式譲渡であれば将来の超過収益力等が加味されて評価されるので他のスキームよりも創業者利益が見込めます。また従業員の雇用を守ると共に、より大きな企業の所属となることで雇用の安定と活躍する場を提供するメリットがあります。
さらに現在の日本社会の大きな問題の一つである後継者問題に対してもM&Aは有効な手法といえます。
関連記事について
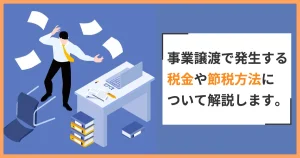
M&Aのデメリット
一方、M&Aにおけるデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。こちらも双方の立場から見てみましょう。
買収(譲受け)側のデメリット
M&A実施後に、貸借対照表上には記載されていなかった簿外債務が発覚するケースもあります。
その様なリスクを回避するためにも、買収先企業の財務リスクを確認しましょう。M&A実行前には買収監査(デューデリジェンス)をするのが一般的です。
売却(譲渡)側のデメリット
売却側のデメリットとしては、想定していた金額よりも低い価格で譲渡しなければいけないケースもあります。業界に詳しいアドバイザーや専門家の助言がなければ売り時を逃してしまうことが多々あります。また買収後に今までの取引先との条件が変更になり、クレームやトラブルになるケースも見受けられます。
まとめ| M&Aは目的を明確にして臨もう

近年は、中小企業の高齢化による後継者が不足している問題からM&Aへのニーズは急速に高まっています。
しかし日本においてはまだまだプレーヤーが少ない状況です。中小企業からのニーズはあるものの、実施までのハードルが高いので中々手が出せない現状です。
その様な課題をクリアしていくには、実績や経験豊富なアドバイザーと巡り合い、信頼できるパートナーとマッチングすることが成功の肝になるでしょう。M&Aを成功に導くにはまずは専門のアドバイザーにサポートしてもらうことをお勧めします。